- Home
- ハラスメントの予防と対策サービス一覧
- 性的マイノリティ理解促進のための対策
ハラスメントの予防と対策サービス性的マイノリティ理解促進のための対策
性的マイノリティ理解促進のための対策
2017年1月1日より、性的マイノリティへのセクハラ(セクシュアルハラスメント)発言も、措置義務が課されるようになりました。
また、2023年6月23日には、LGBT理解増進法(正式名称:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が公布・施行されました。性的指向や性自認の多様性への国民の理解を深め、寛容な社会を実現することを目的とした理念法で、性的マイノリティの人々も「かけがえのない個人」として尊重されるべきであるとしています。
そのような中、私どもは、誰もが自分らしく生きられる、能力発揮ができ、企業、そして社会に貢献できる職場をつくるために、お客様が直面する様々な課題にお応えしています。
- セクシュアリティとは
以下の4要素で構成されます。
- 性自認(自認する性): どの性別を認識するかを表す
- からだの性(生物学的性): 身体的特徴や、性染色体、内外性器の状態等を表す
- 性的指向(好きになる性): どの性別を恋愛の対象とするか/しないかを表す
- 性表現(表現する性): 服装や行動、振る舞いなどからみる社会的な性別を表す - SOGIとは
性的指向 Sexual Orientationと、性自認 Gender Identityの頭文字をとった言葉で、国連や日本の国会など、全ての人の人権にかかわるテーマとして考える場合に使われています。 - 性的マイノリティ(LGBTQ+)とは
SOGIのテーマにおいて、典型的な「男・女」に限らない性のあり方をしている少数派の人たちのことを「性的マイノリティ」と呼びます。LGBTQ+は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングもしくはクィア(※)の頭文字からなる言葉です。
(※) 性自認・性的指向が定まっていないことや、あえて決めていないことをクエスチョニングと言い、クィアとはヘテロセクシャルでない人々およびシスジェンダーでない人々の総称です。
「性的マイノリティ理解増進には、誰もが自分らしく働ける職場を目指すという会社の姿勢が大事です」
-
性的マイノリティに関する認知は低い
性的マイノリティの認知は、日本ではまだまだ低いのが現状です。しかし人口の約10%が性的マイノリティに該当する※1ことを知れば、身近なテーマであることが実感できるでしょう。性自認や性的指向※2は、だれもが持つ基本的人権の一部です。性的マイノリティであることで悩んだり苦しんだりすることなく、誰もが働きやすい職場を作るために、正しい知識を広めることが最も重要です。
※1LGBT総合研究所調べ
※2性的指向=人の恋愛・性愛がどのような性別を対象とするか
性自認=性に対する自己認識 -
LGBTQ+/SOGI理解促進のために企業がすべきこと
正しい理解を広めるための教育研修は必須です。セクハラ防止に関する措置義務に含まれていることを考えれば、新たな周知徹底はもちろんのこと、性的マイノリティに関するからかいや冗談を引き起こさないために、十分な時間をとった教育研修が求められます。
また、相談窓口担当者への教育、更衣室やトイレの利用に関するルール作り、今後増加する同性パートナーの福利厚生利用についての規定づくり等も急がれます。 -
自分と異なる他者を認める企業文化をつくる
「性別は男性・女性に二分されることが当たり前」として過ごしてきた人にとって、「多様な性」の存在をすぐに理解することは難しいかもしれません。しかし、現実に多様な性を生き、同性同士のカップルとして子育てをする家族が世界中にも多く存在しています。
自分とは異なる他者の存在を認めず、排除することはハラスメントにつながります。多様な生き方や価値観を認めることで企業価値を高める「ダイバーシティ経営」の実践に向け、性的マイノリティへの理解増進は不可欠です。
職場の性的マイノリティ理解促進により得られる3つの成果
-
 3つの成果
3つの成果
-
1.理解促進LGBT/SOGIについての正しい理解促進
-
2.問題抑止セクシュアルハラスメント問題の抑止
-
3.能力発揮多様な個人の能力発揮~ダイバーシティ経営への理解促進
クオレの6つの特徴
-
1.カスタマイズ提案
職場の状況やご要望に応じて、お客様独自のカスタマイズプランをご提案
-
2.豊富な経験と実績
年間約750件の研修実績とのべ3000社以上のコンサルティング実績
-
3.パワハラ(パワーハラスメント)対策の第一人者
パワハラという言葉の発案・定義して以来、ハラスメント対策のパイオニアとして多種多様な業種、業態の状況を熟知
-
4.中立的な視点
被害者と企業のどちらかに偏ることなく、中立的な視点で企業と従業員が共に成長できるためのアプローチを実行
-
5.専門家集団
企業経験がある産業カウンセラー有資格者が相談員。経験豊富な講師陣。弁護士、社労士と連携
-
6.高い評価と信頼
大企業から中小企業、行政などからのリピートオーダー多数。厚労省委員等にも度々就任
性的マイノリティの理解促進、なぜ難しい?
職場における性的マイノリティへの理解は、マイノリティ(少数派)であるがゆえ多数派からの理解がなかなか得られない、数が少ないために存在が認識されにくいなど、多数派・少数派という「パワーの差」がそこにあります。その「差」に基づく、正しい知識不足・個の尊厳否定・多様性の否定などが性的マイノリティへのセクハラ行為に発展する可能性を含んでいるため、職場における多数派が行為者になりやすいと言えます。
性的マイノリティへのセクハラのきっかけ
- 物理的な人数の差
- 職場でタブー視されるテーマ
- 知識不足 等によって発生

性的マイノリティへのセクハラ行為の背景となるもの
- 正しい知識の不足
- 個の尊厳否定
- 多様性の否定
- 個々の価値観や強い決めつけ、思い込み
- 文化・歴史的観念

求められる対策
性的マイノリティは13人に一人存在していると言われています。このことから一定数以上の人数を抱える職場においては、どのような業種であっても、性的マイノリティへのセクハラ行為が起きてもおかしくない、と言えます。
性的マイノリティへのセクハラが起きてしまうと・・・
- 社員の働く意欲の低下
- 優秀な人材の流出
- 労働紛争・不正・事故
- 社会からの信頼失墜
- 生産性の低下
- 人材確保の難航
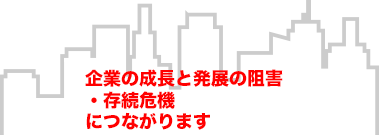
企業における性的マイノリティ理解の促進は、健全な企業運営と成長のためには、欠かすことのできない責務であるといえるでしょう。
性的マイノリティの理解促進は専門家にお任せください
性的マイノリティへの理解が不足していると・・・
- 能力発揮が妨げられる
セクハラ問題により、性的マイノリティの能力発揮が妨げられる - カミングアウトを強要
理解促進のつもりでカミングアウトを強要してしまう - 信頼を失う
個の尊重が阻害されている職場として、お客様からの信頼を失う。 - 相談に寄り添えない
相談窓口担当者が性的マイノリティの相談に寄り添えない
フォームからのお問い合わせ
他のサービスはこちら

ハラスメント・コンサルティング
近年頻発しているパワハラ関連のニュースなどによってパワハラはいまや社会問題となっています。パワハラが被害者に与える心理的ダメージ、その結果企業が背負わなければならない企業イメージの低下、優秀な人材の流出、生産力の低下など、パワハラが企業へ与えるダメージの大きさは残念ながら想像にたやすいと言わざるを得ません。

セクハラ対策
男女雇用機会均等法が施行されて以来、セクハラ(セクシャルハラスメント)に関する知識は教育研修等でかなり浸透していると思われますが、一方で「セクハラ被害を受けた」という相談は減少していません。被害者も、女性ばかりではなく男性の被害も増える傾向にあります。

パワーハラスメント対策
2001年にパワーハラスメントということばを弊社が考案し提唱して以来、その概念が日常に浸透する一方で、パワハラ(パワーハラスメント)の内容、レベルはますます多様になっています。 そのような中、ハラスメント対策のパイオニアとして多数の企業様にコンサルテーションをさせていただいております。

マタハラ・ケアハラ対策
2017年の法改正により、マタニティハラスメント、およびケアハラスメントの防止についても措置義務化され、管理職のみならず同僚同士、女性同士のハラスメントについても企業の責任が問われています。

カスハラ対策
BtoBカスハラ対策のポイントは、自社の従業員がカスハラ被害に遭った場合、会社としての対応を万全にすることです。企業は、トップからのメッセージや研修などを通じてその姿勢を社内外に示すことで、カスハラ被害を未然に防ぎ、自社員によるカスハラ行為を防止します。

ハラスメント防止・予防対策
昨今、ハラスメント問題は、ニュースなどで取り上げられないことがないほど、珍しくない現状となりました。このことは、いつ職場でハラスメント問題が発生してもおかしくない、とも言えます。

ハラスメント相談体制強化のためのサービス
2017年1月から、マタハラやケアハラについても事業主に措置義務が課されることになりました。また、事業主が講ずべき措置には「その他のハラスメント相談と一元的に受け付け、対応することが望ましい」とされ、企業のハラスメント相談窓口の適切な対応が重要になっています。

ハラスメント問題対応
ハラスメント問題は、どれだけ予防に尽力していても、絶対に起きないとはいえません。万が一起きた場合に備え、その対応策を万全にしておくことは企業のハラスメント対策を推進するうえでの安心につながります。問題が起きたことよりも、その問題への対応により、従業員・取引先・顧客を含め、社会の企業に対する信頼度は強まったり揺らいだりするものです。

女性活躍推進・ダイバーシティ対策の概要
今や企業の成長と発展に不可欠な要素となった、企業のダイバーシティ対策。 その中心的な役割を担っているのが、女性活躍推進施策です。301人以上の企業は、女性活躍推進法により、女性の活躍の場を広げる施策を具体的に策定することが求められています。

コンプライアンス対策
2017年3月、消費者庁より「公益通報者保護法」ガイドラインが改正されました。企業の存続を脅かすコンプライアンス問題を早期に発見・解決するためにも、内部通報を放置しないような体制づくりや通報内容など秘密保持の徹底、通報内容の透明性などが強化され、企業にも通報制度の周知や教育を促進することなどが推奨されています。

社外相談窓口
どんな職場にもトラブル発生の可能性は潜んでおり、働く人たちの悩みはつきないものです。大ごとにしたくないという気持ちや雇用不安などから、社内では相談しづらいという人も多く、問題を深刻化させてしまいます。

ハラスメント研修
長年ハラスメント問題を調査・研究し、1999年からセクシュアルハラスメント研修、2003年からパワーハラスメント研修を行ってきたこれまでのノウハウを活かし、職場の状況や、ハラスメント防止対策の推進段階に合わせた研修内容のご提案をしています。

行為者行動変容プログラム
パワハラ行為者(加害者)の行動変容を促すサービスです。ハラスメントリスクが高いと思われる管理者に、予防として実施することも効果的です。

個別面談プログラム
受講者が自分自身を知ることを促す「内省型のオンラインプログラム」です。仕事の流れや考え方・行動などを客観的に振り返り、見つめ直すことで、これまでの自分自身に気がつき、自分を知るきっかけにしていただきます。

職場環境調査(アンケート/ヒアリング)
職場環境調査(アンケート/ヒアリング)によって組織の実態を把握し、現場の声をハラスメント防止策として職場づくりに具体的に生かすことはとても重要です。それぞれの企業の状況に合ったハラスメント対策が可能になります。

事実調査ヒアリング代行
パワハラ等が発生した際に、客観的な立場でヒアリングを行い、クライアント企業様の適切な対応を実務的にサポートいたします。

ハラスメント対策チェック
自社のハラスメント対策の現状を把握し、今後取り組むべき施策のみならず、何から手を付けるべきか、その優先順位もお伝えすることで、ハラスメント対策担当者の取り組みをご支援いたします。
