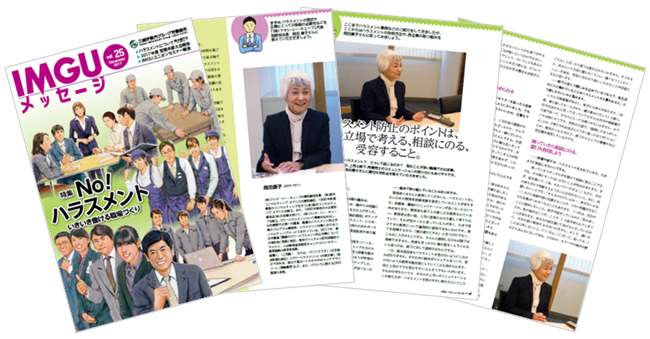講演
講演テーマ
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が2022年4月より中小企業でも義務化され、大企業と合わせて、すべての企業においてハラスメント対策が義務化されることになりました。
ハラスメント対策の総合コンサルティングを提供しているクオレ・シー・キューブでは、20年以上前に「パワーハラスメント」という概念をいち早く見出し、「パワハラ」という言葉をつくった本人(弊社代表・岡田康子)による講演が、その説得力の高さによって多くの企業の皆様よりご用命いただいております。
本ページでは、3000社以上のハラスメント対策コンサルティングの実績より、企業のハラスメント対策の最新事情を具体的な事例も交えてお話しする講演テーマをご紹介します。
皆様の職場での講演・研修に是非、お役立てください。
《これまでの講演実績一覧》 ※随時、更新中です
経営トップ向け
- 人材リスクマネジメントとしてのハラスメント防止
- VUCA時代の人材マネジメント
- 先進企業の成功事例から学ぶハラスメント対策
- パワハラ防止法と企業に求められるハラスメント対策
- 経営陣のハラスメントリスク
- ハラスメント問題の他社動向
- ビジネス環境の変化とマネジメント
- 人材マネジメントとトップの責任
- 経営トップのためのメンタルヘルス
- ダイバーシティ経営とインナーダイバーシティ®開発
- 新事業の創出とイノベーション人材の育成
人事・人材開発・ダイバーシティ・コンプライアンスご担当者向け
- ストレスチェックを使った職場変革
- 行為者対応から学ぶハラスメント対応
管理者向け
- ハラスメントにならない部下指導
- 円滑な人間関係ができる職場づくり
- 職場のハラスメント防止のためのコミュニケーション円滑化
- 働き方改革とインナーダイバーシティ®開発
- 女性のモチベーションを高めるために
一般向け
- 職場のハラスメントとコミュニケーション活性化
- 自分で選ぶ、自分で決める~組織に貢献できる人材になるために
紙面講演
企業や組織の社内向け媒体(広報誌、社内報、CSRレポート等)のコンテンツとして、岡田と企業トップとの対談、対策推進メンバーとの意見交換などを掲載いただいています。
紙面講演のベネフィット
- 印刷物として残る
- 期日を問わず、いつでも振り返ることができる
- 一度にリーチできる人数が多数
三越伊勢丹グループ労働組合 IMGUメッセージ 2017年12月より
当日は、三越伊勢丹グループ労働組合様より、ご担当者・ライター・カメラマンが来社されました。主にご担当者よりご質問いただき、岡田がお答えする形で対談は進められ、原稿はメールで確認させていただきました。
講師紹介

岡田 康子
株式会社クオレ・シー・キューブ
取締役会長
TAやゲシュタルトセラピ―などの心理療法を学び、コミュニケーションやモチベーションの向上を図る研修を行う㈱総合コンサルティングオアシスを設立。その後、社内起業研究会を主催し、新事業ツールを開発。不確実性下の事業マネジメント方法を確立。それらを使って研究開発や新事業、社内ベンチャー支援のコンサルティングを行う。また、女性活躍支援というミッションを掲げ、東京中小企業投資育成(株)の投資を受けて(株)クオレ・シー・キューブを設立。現在ハラスメント対策の他、不確実性下での経営戦略、人材育成などに関する講演を行う。
・厚生労働省「中小企業におけるハラスメント相談体制実証事業検討委員会」委員長
・厚生労働省「カスタマーハラスメント・就活ハラスメント等防止対策強化事業」検討委員会委員長
・厚生労働省「中小企業におけるハラスメント相談体制実証事業検討委員会」委員長
・厚生労働省「カスタマーハラスメント・就活ハラスメント等防止対策強化事業」検討委員会委員長

稲尾 和泉
株式会社クオレ・シー・キューブ
取締役
同シニアコンサルタント
官公庁、自治体、金融機関、製薬企業、小売業、情報通信企業、機械、食品、メーカーなど、幅広い業界企業での研修を担当。セクシュアル・ハラスメント防止、パワー・ハラスメント防止、コミュニケーション、ハラスメント相談窓口担当者スキルアップ、ダイバーシティ・女性活躍推進の分野において研修実績多数。
・厚労省 平成27年度 サポートガイド改訂に向けた調査研究委員会 委員
・厚労省 平成28年度~31年度 パワーハラスメント対策企画委員会 委員
・人事院 平成31年度 公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会 委員
・東京都 令和5年度 産業労働局TOKYOノーハラ動画コンテンツ『カスハラ』解説
著書に「上司と部下の深いみぞ~パワー・ハラスメント完全理解」(紀伊国屋書店)共著、「パワーハラスメント」(日本経済新聞出版社)共著、「あんなパワハラ こんなパワハラ」(全国労働基準関係団体連合会)著などがあり、雑誌、専門誌等への執筆多数。
・厚労省 平成27年度 サポートガイド改訂に向けた調査研究委員会 委員
・厚労省 平成28年度~31年度 パワーハラスメント対策企画委員会 委員
・人事院 平成31年度 公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会 委員
・東京都 令和5年度 産業労働局TOKYOノーハラ動画コンテンツ『カスハラ』解説
著書に「上司と部下の深いみぞ~パワー・ハラスメント完全理解」(紀伊国屋書店)共著、「パワーハラスメント」(日本経済新聞出版社)共著、「あんなパワハラ こんなパワハラ」(全国労働基準関係団体連合会)著などがあり、雑誌、専門誌等への執筆多数。